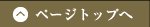戦乱と日本刀 武器として性能の高い刀剣とは
投稿日:2025年08月27日(水)
<各時代から>
日本において武器とは何からはじまったかと言われれば、まずは石器です。遺跡から銅剣などが出ておりますが儀礼的なものが多く、日本人は黒曜石を長い間刃物として使用しており、その数や質から当時から相当切れ味に気を使っていて後のモノづくりへの熱意の片鱗を感じさせます。その後、鉄剣の時代となり、世界的にも古い時代から鉄を鍛えるということを行っているようです。その後、蝦夷の蕨手刀などの影響があり、片刃の反った刀剣、所謂「日本刀」が生まれています。ただ実際の戦場では、平安時代、そして続く、鎌倉時代でも主要な武装は弓であり、次に徒を中心とする従者の得物は長巻(薙刀)で、貴人は馬上で太刀を佩くというのが主要な軍容でした。
鎌倉時代の終わりのきっかけとなった元寇では足場が悪い戦場もあり、徒の武装がより重視されるようになったようで、長巻と太刀の兼用として身幅が広い豪壮な太刀がでてくるようになります。この豪壮な得物は戦乱の時代になる度に必要とされて、その後の南北朝時代や戦国時代、最後は幕末に多く出現します。その結果として、鎌倉時代を通じて、一文字や薙刀が流行りましたが、元寇があった鎌倉中期をきっかけにして長船が活躍を始めます。これは質より数が重視されるようになった経緯をあらわしているようで次第に時代が若くなるにつれて、鉄質は徐々に悪くなっていきます。
続く、南北朝時代の終わりには長船で規格的な作風の小反りが多く作刀されるようになります。これはその後の戦国時代の終わりと江戸時代の最初にも同じような傾向が見られます。これは戦い前夜の時点では、こういうのが必要では?といろいろ手を出して作ってしまい、果たして戦争がはじまるとこういうものさえあればいいと必要性の認識の極端化があったのではないでしょうか。その結果、一文字や青江は組織化された長船に吸収され、大薙刀の勇壮な部隊は消えて、槍が主要な近接武器になります。その後の歴史でも幕末でも活動時期が比較的早めの直胤は比較的各種いろいろ作っていますが、その後の弟子たちの作など戦っている時期のものは前時代に比べて、ある程度規格的なまとまりができてきたようで変則的なものは少なくなります。また、この南北朝時代の戦乱のなかで特殊な短刀の発展形として、菊池槍が登場し、以後戦場の主役は槍になっていきます。弓も火縄銃の数が揃う戦国末期まで主用な武器でした。槍と火縄銃によって終わった戦国時代ですが、江戸時代になると戦乱のない時代の為に様々なルールができてきて、日本刀の社会的、身分的な活用方法が決まってきます。そうしてむしろ戦国時代より日本刀がより必要になってくるようになります。なお戦国時代は質より数が必要でしたが、刀が侍という階級に必須になり身分をさすものになると度を越した粗悪品はふさわしくないということで品質の選別が行われたと見られます。そこで武用のために斬れる刀を選ぶため、そして社会的に必要な財として美術的な観点を含めて、かつてからあった本阿弥の鑑定が必要となってきました。ここですべての刀で斬れ味を試すのは現実的でないので、一部の刀剣を試してそれを資料に斬れ味を探ろうということが江戸時代から行われ、その一つが山田浅右衛門の格付けです。その後、西南戦争の教訓と精神的な支柱として軍に軍刀が多く取り入れられると、各地の団体で試し斬りが行われるようになると、武道の一環として日本刀の試し斬りが必要となっていきました。
<次に性能とは、斬れ味とは>
日本刀がまず刃物であるという点から、目的としてなにがあるかと問えば、「まず斬る」、そして太刀なら特に「突く」ということが目的です。そしてこの目的を果たす為にはまず避けたいのが「折れる」ことです。そこで問題なのは斬れるということは「硬い」ということで、でどうしても硬いことが必要になりますが、硬いせいで折れる可能性がでてくるということです。そこで内部構造や品質でカバーできなければ折れるのを防ぐ為に硬さを諦めないといけないのですが、そこで硬い部分を必要最小限の場所でムラなく配置することでそれを克服したいというのが日本刀造りの肝となっています。なお内部構造としては、刃鉄と心金の接合具合や柾目にすることで斬る際の力の向きに対応するやり方があります。その他、もの打ちの部分は斬る部分なので固くしたいので焼きを強くすることが多いです。
この制約のせいで、日本刀造りは斬る対象によって造り分けるということが選択に入ってきます。そのポイントは「硬物斬り」と「柔物斬り」の2パターンです。
巻き藁一つくらいでしたら区別するほどではないですが、鉄やもっと柔らかいですが竹が硬いほうで、巻き藁やもっと大変なのでは綿などが柔物斬りです。
備前や関など、映りのあるのは柔らかいので硬物斬りや突きに適し、寒さにも強いです。
相州や現代刀は硬いので柔物斬りに適し、鎬が低くて幅が広いなど形状が良ければ巻き藁五個斬りも可能でしょう。
それぞれ使い分けられれば良いのですが、それが難しいときは身幅を広くしたり、重ねを厚くしたりする他、長さを短めにすれば耐久性を上げられます。そのため、平造りで長い刀は少ないのです。
次に形状をかえることで用途にあった能力を高められます。例えば薙刀は斬るのに特化した形状で戦前の記録ではどんな刀より斬れたそうです。そして突くのに特化した形状が槍です。なおどちらも突くだけ、斬るだけでなく、両方の使い方ができ、さらに柄の長さを長くすることで間合いを広くとれるなどの利点があり、性能という面では申し分ないことだったでしょう。刀、太刀に関しても斬る他に突く、同じく長くすることで間合いもとれますが、訓練や素養を要求されるという点に大きな違いがあったようです。なお、有名な山田浅右衛門の業物表は試刀術の関係上、柔物斬りを重視した傾向が強いです。平肉がついていない関や肥前刀が多く含まれていることからそのことがよくわかります。