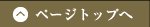直刃と地肌、地鉄の関係性<山城、大和から備前、美濃、そして新刀の代表、肥前刀へ>
投稿日:2025年01月26日(日)
新刀以降の刀工が一人で刃紋と地鉄を関係なく自由に造っているように見えるので忘れられがちですが、古刀では、それぞれの刃紋にあった地肌というものがありました。それが「大乱れには大肌に鍛える、直刃、小乱れには小肌に鍛える」ということでしたが、新刀ではほとんどが小肌の綺麗な地鉄で匂い口の深い大乱れが多く、これらは本来、よく言われる五カ伝の外であり、本阿弥光遜は新刀特伝と名付けています。このように大肌と小肌はどちらがいいとは比較できないものであり、新刀以降は地肌の組み合わせなどの技術によって不可能を可能にしており、その性質によって多くは匂い口の特徴が刃縁に顕われます。
直刃は刃紋の基本であって、それ以外は乱れ刃と考え、刀の顔である帽子の刃紋の乱れかたに注目してください。次に刃紋の焼き、つまり匂い口自体に注目すると、大まかに締まったもの、フックラとしてもの、深いものに分類できます。締まったものは鉛筆で書いたような太さ、太いものは鉛筆の芯の腹でこすったような幅を想像してください。フックラはその中間、マジックで書いたような幅が参考になります。次はその匂い口がかすれていたり、崩れていたりした部分があるかさがしてください。そこが汚く見えたらそれは匂い口のムラです。これがあまり目立つようだったり、出方を見て下さい。そこに特徴がわかってきたなら、それがその刀の特徴でもあります。そうすれば同じように見えていた刀にも少しづつ違いがわかるようになると思います。
個別の刀工では、山城や大和は姿は宝刀然として優美ですが、金筋が匂い口になったかのような強い匂い口のものがあり、地肌も備前より沸が、つまり焼きが強いものが多いです。備前は最初はすべてバランスのよい、見て上品なもので、古くは腰反が迫力がありながら優美なものを造っています。ただその後、戦国時代では実用的な、反りが浅い片手打ちが多くなり、地肌も映りがあまりでなくなっていき、南蛮鉄を使っていたのか、刃も関やその後の肥前刀のような小沸出来が多くなっていきます。むしろその後は高田や大阪新刀に備前刀らしい刀を造る刀工がでるようになります。関では備前で片手打ちが流行して時期と同時期から作刀が多くなり、兼定、孫六の他、兼房、兼常などの多くの名工がでます。これらの刀工は直刃や湾れなど単純な刃紋が多く、末備前に近い作風ではありますが、沸がより強く、相州伝として知られる出来を得意としており、その華やかさや斬れ味が戦国時代から安土桃山時代を通してもっとも人気となります。それが江戸時代もつづいて主要な作風なり、綺麗な地肌と沸の強い刃が幕末に再度備前伝が流行するまで主要な作風となります。幕末以降でもこの相州伝と備前伝をあわせたような作風が人気であり、それが水心子一門と清麿や宮入、吉原一門として知られています。