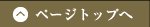古刀の旅
投稿日:2025年09月25日(木)
今回は古河での鑑賞会にあわせて、鉄の歴史に着目して想像の古刀の世界を旅してみたいと思います。特に鉄に着目した古刀の旅となりますので、ここでは剣と太刀の区別はしておりません。剣も上古刀と言われるので古刀の一つと考えます。
まず古い製鉄の歴史がある吉備国から鉄の旅は始まります。後の歴史では吉備津神社を中心としますと西方を備中、南方を備前と分けられますが、かつては岡山市の低地部分は海でしたので吉備国の中心は備中と備前にまたがっていました。そこの山間で鉄は造られて吉備国の国力はどんどん高まり、のちの備前長船の礎となります。当時は現在より寒冷で、映りがある寒さに強い備前伝はここからきていると考えられます。
そして次にその鉄が当時の都である大和に運ばれ、大和鍛冶がはじまります。大和では剣がよくつくられ、僧兵のために太刀もつくられはじめたことでしょう。千手院などお寺に関する刀工が多いです。また荘園どうしの繋がりでその技術が後に越中や関に伝っており、越中では仏教用語を冠する刀工(宇多)がいたり、大和で包(カネ)と名乗る刀工が関で同じ訓読みである兼(カネ)と名乗ったり、銘字からもその痕跡を感じさせます。そして都が京になったころには、東北から連れてこられた俘囚鍛冶(舞草刀工)の手によって山城伝の基礎がつくられています。三条鍛冶などに綾杉肌があるのはその影響と言われます。
また同じく俘囚鍛冶がいた鎌倉で京の影響を受けながら相州鍛冶が誕生します。鎌倉武士の気風を受けてか、相州鍛冶の作風は最も覇気があると言われています。大和出身の長谷部がその橋渡しをしたと言われており、長谷部は鎌倉で相州伝を身に着けてから京へ行っています。最後に近畿圏と関東をつなぐ交易が盛んな東海地方で、木曽の木材と水を生かせた美濃に関鍛冶が活躍するようになります。関はほぼ南北朝時代からと比較的に後から始まった刀工群なので、型を多用して省力化を行っていたりと現代のモノづくりの基礎となる部分が多々見られます。
別記として、吉備国の頃から技術交流が多かった九州は作刀の歴史が古いせいか大和伝色が強く、波平などを見ても独自の特色を持っています。
<鑑賞刀>
(備前)一文字、(大和)宇多国宗、(山城)長谷部、(相州)広光、(美濃関)村正