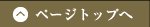元寇と戦乱後の日本刀
投稿日:2025年07月30日(水)
<日本刀の作域の変遷から見える戦乱中の試行錯誤と戦後の作風のまとまりについて>
鎌倉時代の武士の主要な武装は弓であり、次に徒を中心とする従者の得物は長巻(薙刀)で、貴人は馬上で太刀を佩くというのが主要な軍容でした。元寇では足場が悪い戦場もあり、徒の武装がより重視されるようになりますと長巻と太刀の兼用として身幅が広い豪壮な太刀がでてくるようになります。この豪壮な得物は戦乱の時代になる度に必要とされて、その後の南北朝時代や戦国時代、最後は幕末に多く出現します。その結果として、鎌倉時代を通じて、一文字や薙刀が流行りましたが、元寇があった鎌倉中期をきっかけにして長船が活躍を始めます。南北朝時代の終わりには長船で規格的な作風の小反りが多く作刀されるようになります。これはその後の戦国時代の終わりと江戸時代の最初にも同じような傾向が見られます。これは戦い前夜の時点では、こういうのが必要では?といろいろ手を出して作ってしまい、果たして戦争がはじまるとこういうものさえあればいいと必要性の認識の極端化があったのではないでしょうか。その結果、一文字や青江は組織化された長船に吸収され、大薙刀の勇壮な部隊は消えて、槍が主要な近接武器になります。その後の歴史でも幕末でも活動時期が比較的早めの直胤は比較的各種いろいろ作っていますが、その後の弟子たちの作など戦っている時期のものは前時代に比べて、ある程度規格的なまとまりがあるように思います。なお正宗に代表される相州刀工のように戦乱に巻き込まれて消えた刀工集団も多くあると思いますが、それも後の戦国末期以外は極端な絶滅は少ないように感じます。