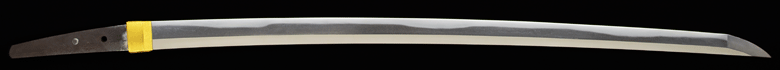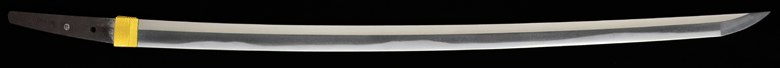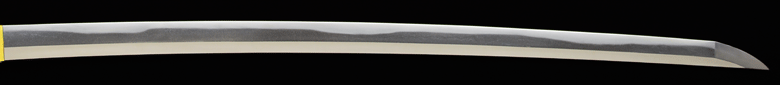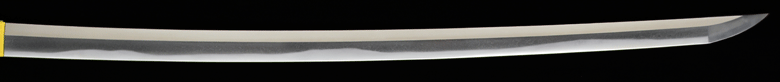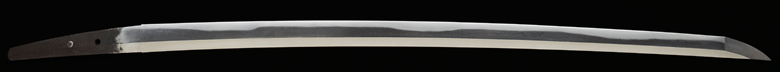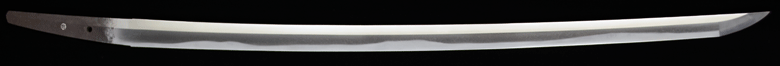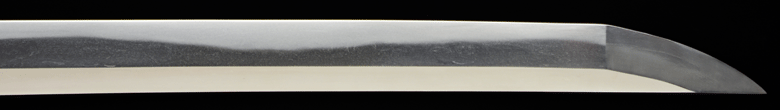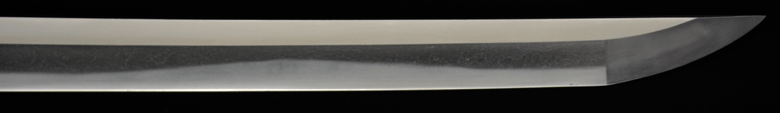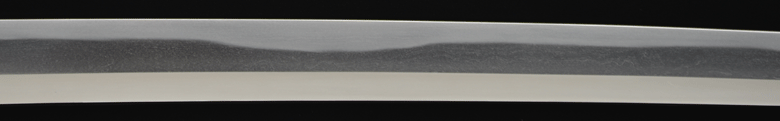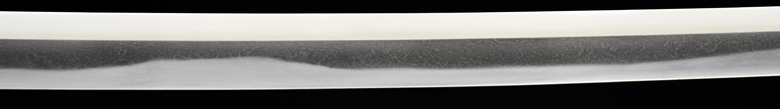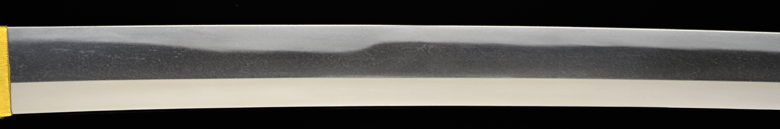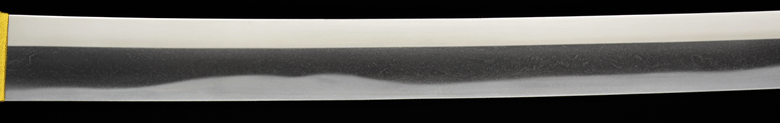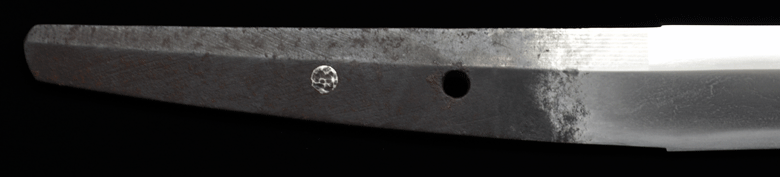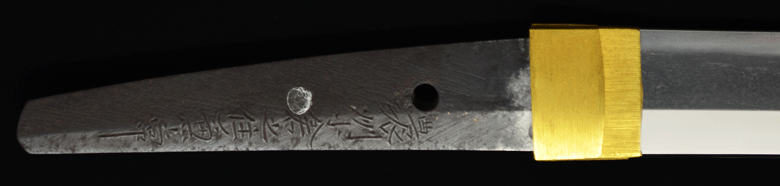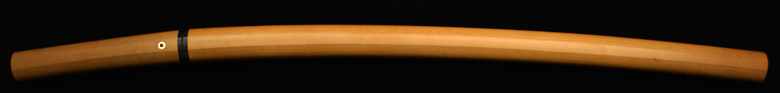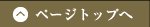兼定、兼元とならぶ美濃伝を代表する関兼常の刀です。本刀は関伝得意の湾れ乱れが古調かつ、力強く冴えており、戦国期の関を代表する名刀です。
兼常は大和千手院の系統といい、関七流の奈良派とされて各代が名工揃いです。そのあまりの斬れ味に「手棒兼常」という異名で呼ばれた他、本工が元亀二年七月に織田信長より関鍛冶総領事の称を貰い関鍛冶の頭領となったことは有名です。現存するよく知られる名作には「中川左平太試銘」という裁断銘入の本多忠勝の子、忠為所持の脇差のほかに、備中国の武将、三村氏の家臣「石川久智所持」の天文兼常の短刀があり、天正十二年には小牧、長久手の戦に於いて徳川家康公の求めで槍百筋を造ったと伝えられており、その品質に多くの武将が信頼をおいており、当時において孫六や兼定に比肩する実力と知名度をもっていました。本作は同工の中でも傑作で、同時代の村正や、後の堀川国広にも比肩する出来が見事です。