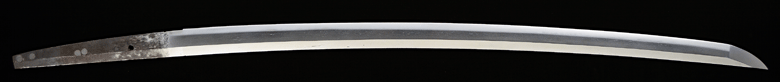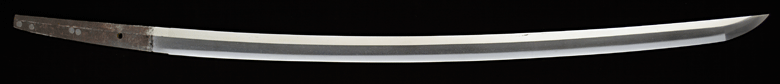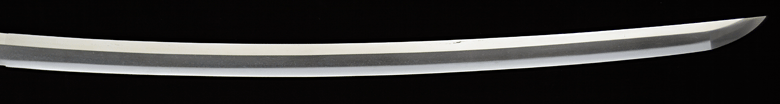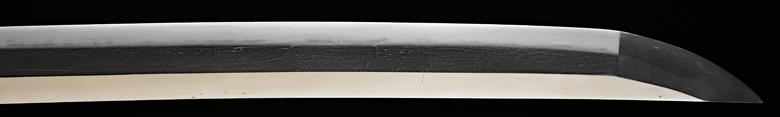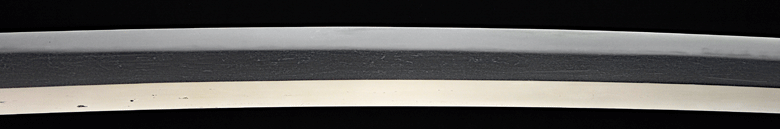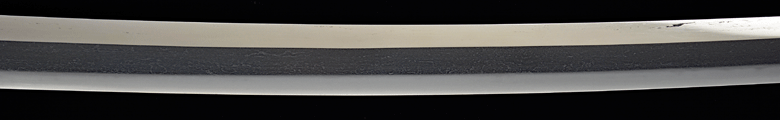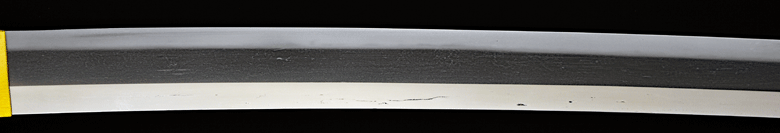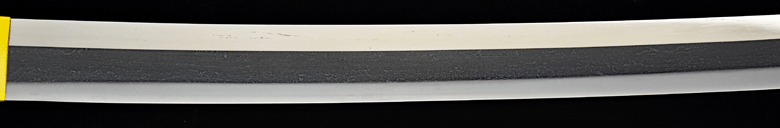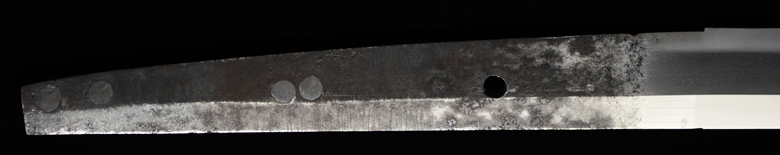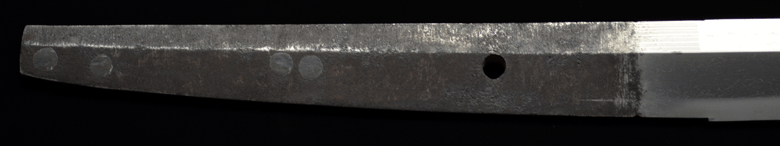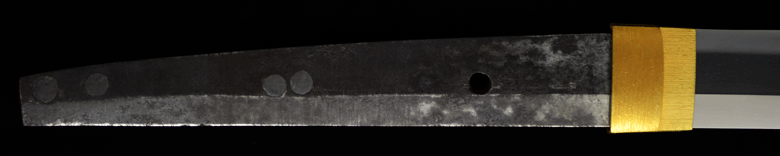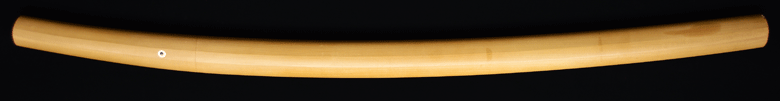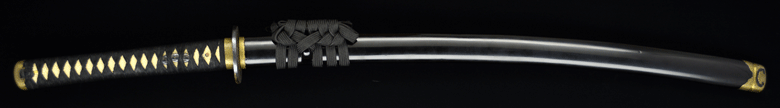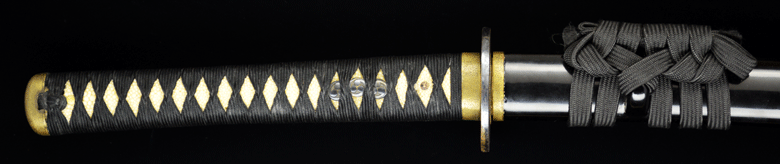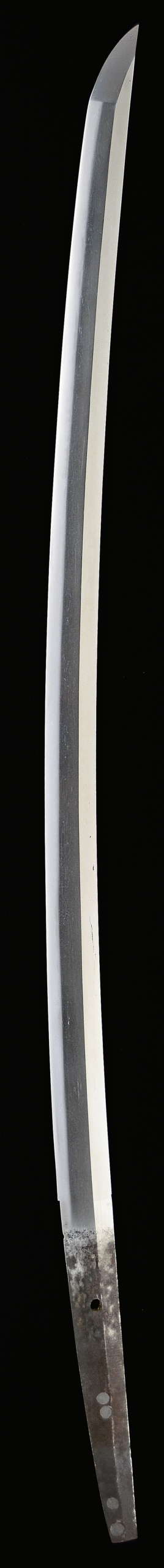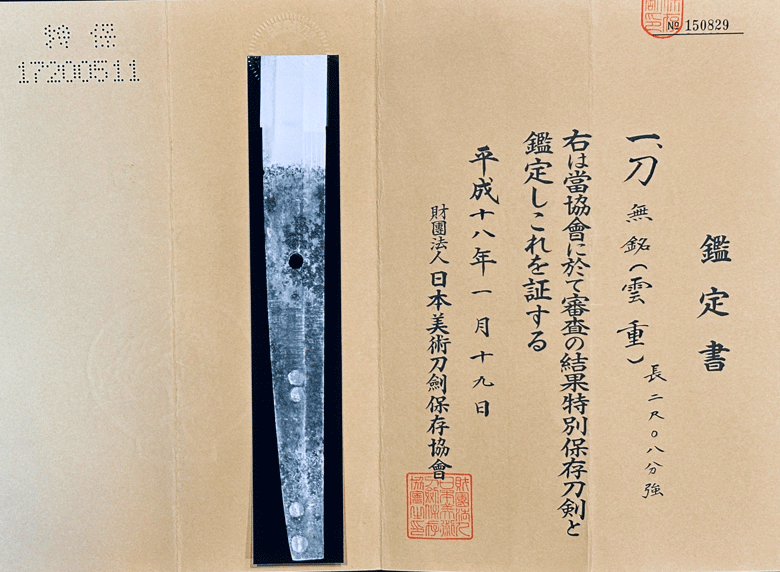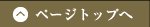鎌倉後期、雲生、雲次、雲重で知られる宇甘(雲重)派の刀です。鎌倉時代後期から南北朝期にかけて、備前国宇甘庄に雲生、雲次、雲重などの刀工がおり、特に「雲重」は大振りな薙刀など、豪壮な作が多いことで知られます。この一派は居住地の「宇甘」から宇甘派あるいは鵜飼派と呼ばれ、その銘に「雲」の字を冠するところより、雲類とも称されています。彼らの作風は当時の長船正系とは相違するところがあり、備前伝の中に山城風があり、さらに隣接する備中青江派の影響も受けており、長船元重などと同じく備前物中でも異色の存在とされます。備前の名作に匹敵する出来に山城風の優美さが加わって、古来より武士に珍重されていました。伊達家伝来の雲次などが知られます。
本作は、杢が立つ幽玄な鍛え肌に匂い深く沸づいた刃が美しい、備前刀ながら山城気質が強い、同派中でも豪壮無比な雲重の傑作です。
Mumei:Ukai
Katana: Bizen no kuni ukai Ju Unrui
late Kamakura period:1333 Bizen