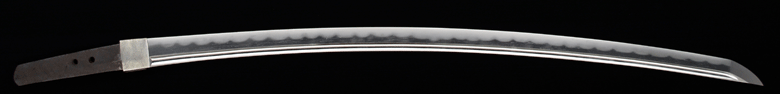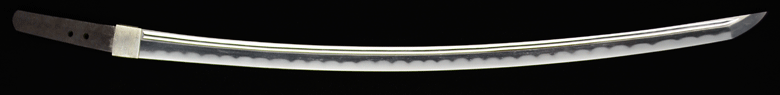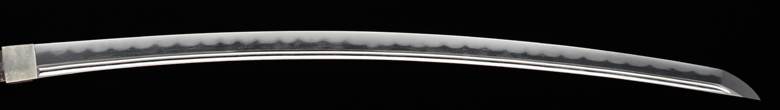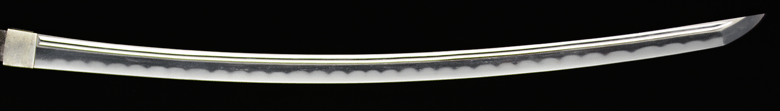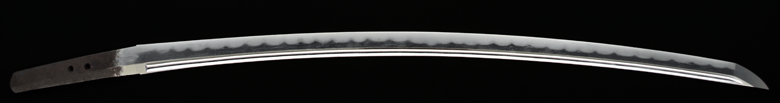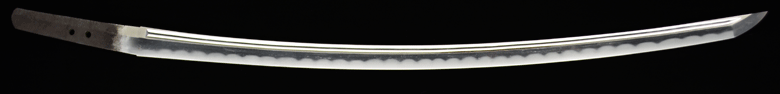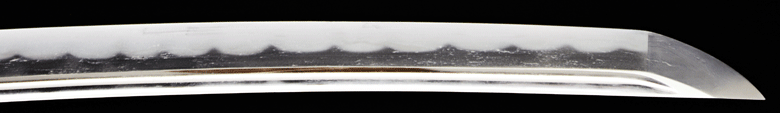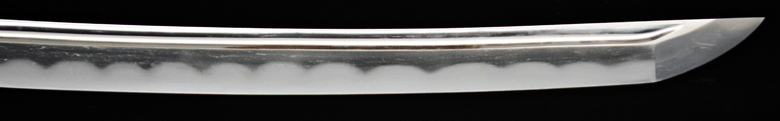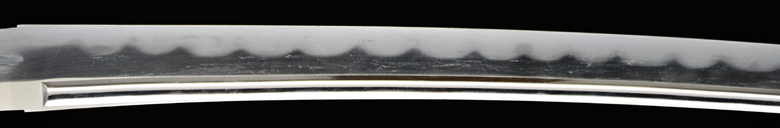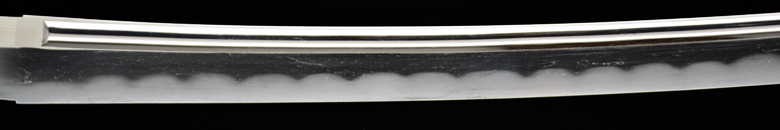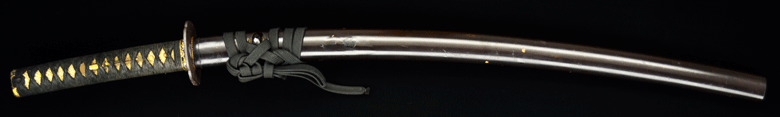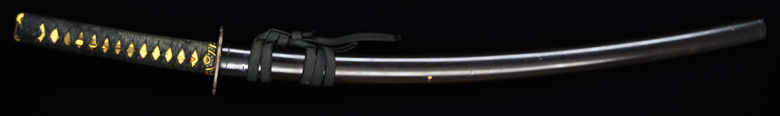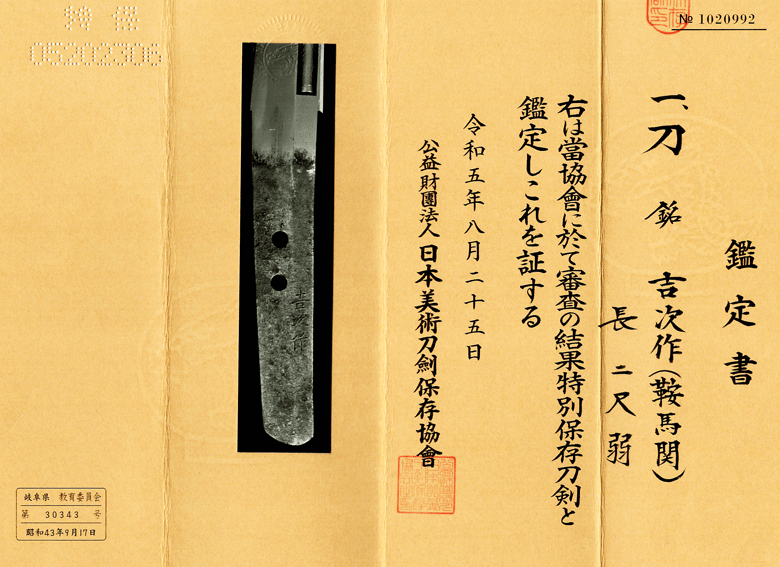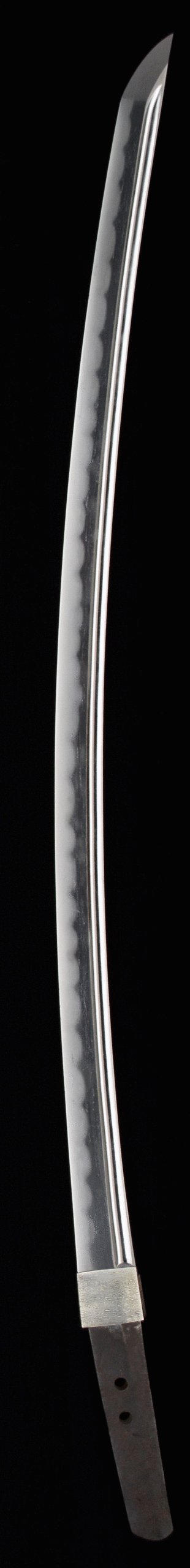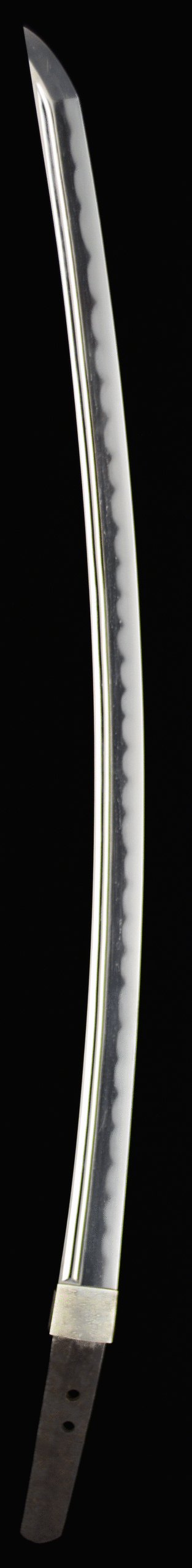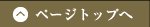特に現存する刀が少なく珍しいことから、幻の刀と言われる、鞍馬関吉次の刀です。吉次は京都の鞍馬寺の門前で鍛刀していたので鞍馬関といい、鞍馬住とある明応八年作の脇差が知られています。名跡は新刀期まで続いており当時の人気が偲ばれます。特に本作の出来はまるで同時代の長船勝光の注文打ちのような出来です。
一説に「古今鍛冶備考」の記述に「吉次の本国は関で鞍馬関と称され、京信国、相州秋広に師事して帰郷した」とあることから、応仁の乱の為に関に移住したと言われます。しかし実際の作風から平安城長吉一門に似る(「刀工辞典」藤代義雄先生)という物証があり、長吉や吉則と同じく本国は京鍛冶で、関や相州に移鎚した後、帰京したとの説もございます。改めて本作を見てみますと備前伝色が強く、三条吉則などにも備前風の作があることから三条鍛冶に有縁のように感じます。鞍馬という名を冠することから、洛内から義経にあやかって移住したとも思われ、作品が稀なことでますます謎が深まる本作は歴史的な資料性が高い一振りです。